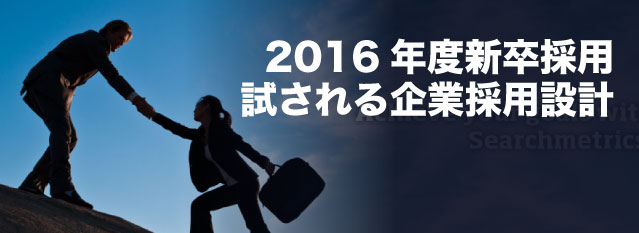2016年度新制度の企業側への影響

2016年度新制度の影響で、企業の採用部門の動きは大きく変わってきます。
経団連の指針に則るのであれば、これまで社内人事で忙しくされていた4月が会社説明会時期と重なりますし、10月に内定式を行うのであれば、8月からわずか2ヶ月で選考・内定出しを完了させるスケジュールとなります。
採用部門の現場での混乱は、少なからず起きるのではないでしょうか。
このように大きく制度が変わる中、それでも今まで通り横一直線並びで広告し学生を待つ方法で良いものでしょうか。
採用部門の最大のミッションは優秀な人材を確保することです。
この機会に従来のやり方を見つめ直し、少しずつではありますが独自路線の採用方法を行う企業が出始めています。
例えば、インターンシップ。
経団連は倫理憲章でインターンシップを採用に利用することを加盟企業に対して実質的に禁じていますが、この縛りがない企業は、応募の対象を大学1年生にまで広げ、優秀な学生をいち早く囲い込もうとする動きもあります。
学生の方にも、まだ頭の柔らかい内に社会で刺激を受け、仕事に対しての抵抗感をなくすことによって、より冷静に自分の目標を設定する準備ができるというメリットがあります。
これからは、大手就職サイトを頼らずに自社が欲しい人材と接触をする、”待ち”から”攻め”の採用にシフトする企業が増えると思います。
ますます内容の勝負になるインターンシップ

インターンの時期も従来の3年生の夏休みから、冬休みや春休みに後ろ倒しになる可能性があります。
一方、もともと経団連のしばりがない企業は、大学1年生にまで広げ、事実上の青田買いを行う企業もいます。
表立って採用活動を行わないまでも、学生との早期接点の場を設けるために、インターンシップを導入する企業が増加すると予想されます。
インターンシップは学生が社会を経験する重要な場所です。学生にとって”社会人”として“大人との会話”をすることはとても刺激的なのです。未熟な部分を目の当たりにすると同時に、会社に入社してから業務上の向き・不向きを予めイメージできます。
この経験は、就職活動だけでなく、入社後にも活かされることでしょう。
実際、インターンシップに参加した学生は、参加企業・参加業種へ入社を決めている人も多いのです。
導入企業が増えるほど重要となるのがプログラムの内容です。ただ実施することを目的に作られたプログラムでは、採用成功はもとより、学生のエントリー確保にすら困難になるという結果になりかねません。
やはり時間とコスト、そして労力をかけて設計・実施するプログラムにこそ、優秀な学生は集まり、その後の採用へ、そして入社後の業務へとつながっていくのです。
攻めの採用~ダイレクトリクルーティングで金太郎飴採用からの脱却~

今までのような、横一直線並びで広告し学生を待つ方法から、大手就職サイトを頼らずに自社が欲しい人材にアプローチする企業も増えてきています。
企業の状況によっては、優秀かどうかだけでなく、既存の枠組みにとらわれず社内に新しい風を吹き込んでもらえそうな人材を求めている場合もあります。例えば、ちょっととんがった人材が欲しいときがあると思います。
従来の大量採用方式のように、一斉に行われるエントリー審査・適性検査などで足切りを行ったりすると、結局は平均的な人ばかり残り、求めている人材はふるい落とされたりします。
企業からターゲット人材にアプローチする場合は、筆記試験は得意ではないが能力が高いといった学生を落とさないために、人材像ごとにメニューを用意するのも良いと思います。そのためには、大手就職サイトへの出稿をやめるなど思い切った改革もありえますし、実際にそのような企業もでてきています。
就職サイト以外にも、社員から出身大学やサークルなどで知り合った優秀な後輩を紹介してもらう方法もあります。
社員から紹介を受けた人事担当者が会い、適性を判断した上で選考に加えるなど、通常募集以外のルートを作ったり様々なやり方があります。
自社に優秀な人材がいるのであれば、類は友を呼ぶというように、優秀な人材が集まりやすい環境といえますので、その人脈を使わない手はないでしょう。
これらの方法には大きなメリットがあります。
それは、直接会社のビジョンを伝えたり、それに共感してもらえるか反応を確認できることです。
これがダイレクトリクルーティングの強みです。
少なくとも、従来の大量・一斉方式よりは相思相愛という形になりやすいので、内定辞退率・早期離職率の低下にもつながります。
学生との早期接点において新入社員を迎える上司・先輩の心構えが必要

最近の若者が心が折れやすいは、家庭も学校も過保護・過干渉という環境で育ってきたからとも言えます。
就職活動で初めて社会の厳しい現実に直面し、メンタル面で厳しい状況に追い込まれた学生も少なくないでしょう。
また、画一化された就活スタイルに慣らされている学生たちは、大多数の企業側も「ソツのない人」を好むという真実を誰よりもよく分かっています。
一度就活に失敗して大学を卒業してしまうと、やり直しがなかなかきかないという日本事情もあり、過度に慎重になっています。
インターンシップやダイテクトリクルーティングなどで、学生と早期に接点を持つ機会がある場合、そんなバックグラウンドがあるということを理解しておく必要があります。
3年で約3割にも達すると言われる新入社員の離職率に、危機感を持っている企業は少なくありません。
しかし学生は、そんな企業以上に採用された後のことを考えています。入社した後この会社でやっていけるか真剣に考え、最初から「離職してもいい」と思って就職活動している人はほぼいないのではないでしょうか。
彼らが企業と接触する時に、そこで働きたいと思う大きな判断材料となるのは「職場に尊敬する先輩・上司がいるか」「上司が自分の成長に関心を持っていると感じているか」などの職場の人間関係にあります。
だからこそ学生との早期接点には、そんな彼らの心に触れることのできるコミュニケーションが必要だということを、上司や先輩たちは理解しておく必要があるのです。
ターゲット人材獲得にはビジネスの潜在能力をあぶり出すESP診断を
わずか数回の面接だけで、その人の持つ能力を見極められますか?
その人は近い将来、会社で実力を伸ばす要素を持っているのか。
そのようなビジネスの本質・資質に関わることとなると、目に見えにくいものなので判断するのは難しいでしょう。
そこで、ビジネス能力を測定する診断をご紹介します。
ハイパフォーマーになれる可能性のある「動機」と「資質」を持ったビジネスパーソンにフォーカスしています。
実際の業績とESP診断結果の間に、極めて高い相関があり、これまでの診断システムと比較して、ダントツに予測性が高い診断システムです。
詳細を見る >>